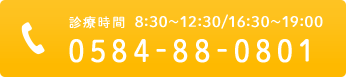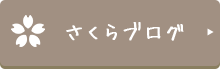珈琲
2025.12.02更新
毎日コーヒーを飲むのが習慣になっている方は多いと思います。
私もその一人なのですが、コーヒーの香りが大好きです

そんなコーヒーにはどんな効果があるのでしょう…
コーヒーに含まれるカフェインには神経や筋肉を刺激する作用があるので、肉体の疲労を回復させる効果があるそうです。
カフェイン効果
:胃酸分泌を促す
:利尿作用 
:覚醒作用
そのほかの効果
:コレステロールを下げる働き
:善玉コレステロールの増加
:喘息発作を抑える
:脂肪分解
:精神リラックス効果
しかし風邪をひいたときには、症状によってコーヒーを控えたほうがよい時もあるので注意が必要です。
▲高熱が出ているとき
▲睡眠が不足しているとき
▲胃腸が敏感なとき
カフェインの

*利尿作用によって脱水症状のリスクが高まる可能性
*覚醒作用によって睡眠の質を低下させるおそれ
*胃酸分泌作用によって胃腸の不調のさらなる悪化
毎日の習慣とはいえ、体調によってコーヒーが美味しく楽しめなかったりするときは控えましょう

投稿者:
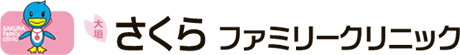
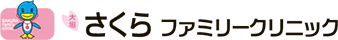
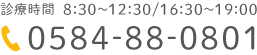
















 。
。